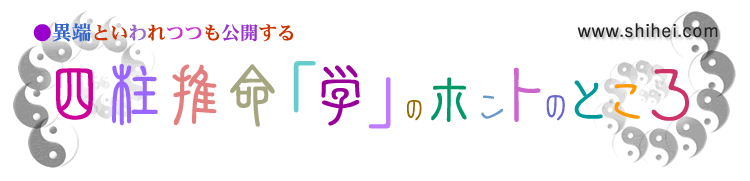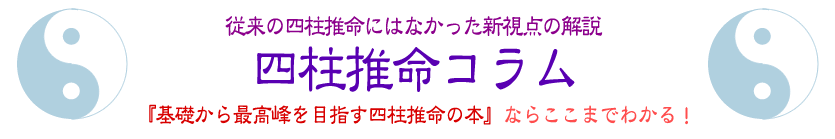
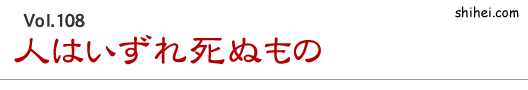
以下の説明を読み、すんなりと理解していただけるのは、私の講義に出席された方と最新刊『基礎から最高峰を目指す四柱推命の本』の読者だけでしょうが、あえて、現状ではまだ少部数しか世の中に流通していませんので、読者の対象が少ないことを承知の上で、こうした形で情報を発信することにしました。
生死の時期は推命では論じることは不能
四柱推命を含めて、運命学を学びますと、最終的には学んでいる本人の寿命はいつまで、という話にたどり着きます。つまり、いつ頃、命を落としかねないような事態になるかを察知することになるのです。
人はいずれ死ぬものとしても、たかが占いで何が分かるのか、という考えはあるでしょう。あるいは、参考にもならない話でしかないと考える人が多いかもしれません。
医学の進歩により、生物的な死の時期は、四柱推命では論じられない面が増えています。以前は死ぬしかなかったような病気も一部医学的に克服されています。しかし、それでも、死という最終的な事象への道筋は、四柱推命で捉えることができるようになっていると考えています。
死に至る推命的な視点は、大運における「五行の非調和」であり、同時に「通変の非調和」が重なりますと、かなり深刻な状態ではないかと考えています。この状態においては、生死に関わる大きな問題が発生すると考えられます。
その根拠は、すでに亡くなっている人々の四柱八字と大運から、論理的に推察されるのです。
「ああ・・・怖ろしい」。四柱推命を学んでいると、どのように自身の死を迎えるか、と考える必要が生じてしまうのです。
こうした究極的とも言える覚悟ができない人は、四柱推命に関わらないほうが賢明ではないかと考えます。逆に言うなら、四柱推命は、自身の人生をきれいに終わらすことができる視点なのかも知れません。
※上記の説明には、本書独自の蔵干の考え方と、格局に代わる」「旺の逆転」という視点が含まれています。詳しくは、基礎から最高峰を目指す『四柱推命の本』を参照してください。
2015・9・26
Since:1998-08-05 /// Last updated:2023-8-2
著作権法に基づき、本サイトの内容を、無断で引用、複製、翻訳、放送、出版、改変、等することを禁じます。
- 参考文献 |
- お問い合わせ
- | 管理人Profile
- |ツイート