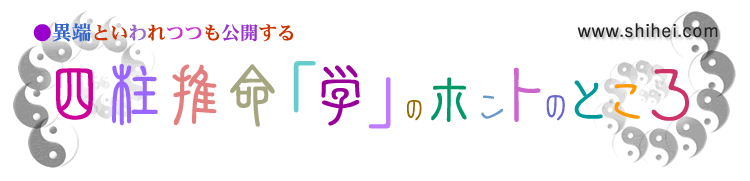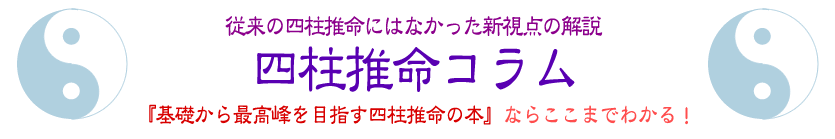
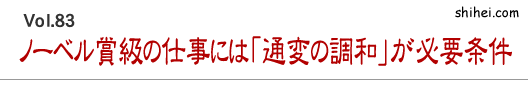
以下の説明を読み、すんなりと理解していただけるのは、私の講義に出席された方と最新刊『基礎から最高峰を目指す四柱推命の本』の読者だけでしょうが、あえて、現状ではまだ少部数しか世の中に流通していませんので、読者の対象が少ないことを承知の上で、こうした形で情報を発信することにしました。
「必要条件」「十分条件」の解説
ノーベル賞を受賞した人の命運を見ますと、その評価された仕事を成し遂げた時に「通変の調和」が成立しているようなのです。ですから、タイトルに「必要条件」と書いたのです。
「必要条件」は論理学の用語で、一般的ではないので、一応、その意味を説明します。
「必要条件」のほか「十分条件」があります。
「優れた研究をした学者がノーベル賞を受賞する」という命題が実現するための条件を考えたときに、ノーベル賞を受賞するという事象は「必要条件」であり、あくまで結果でしかないのです。「優れた研究をする」ことはノーベル賞受賞の「十分条件」ですが、ノーベル賞を受賞することが保障されてはいないのです。
ですから、ノーベル賞を受賞できるような必要十分条件は存在しないのです。こうしてノーベル賞を受賞できるような必要十分条件が存在しないことが、ノーベル賞の権威の保持にもつながっていると理解できるのです。
年と大運のよしあしで受賞は判断できない
さて、ややこしい話はさておき、今年2014年、青色発光ダイオードの研究と実用化が評価され、赤崎勇氏 天野浩氏 中村修二氏の三氏にノーベル賞が授与されることになりました。
日本には、自然科学関係だけで19人ものノーベル賞受賞者がいますが、その幾人かを見てわかることは、受賞対象になった研究を成し遂げた年齢期に「通変の調和」が成立しているのです。
既存の推命では、賞を授与された、年と大運のよしあしで栄誉を判断していましたが、誤りです。こうした栄誉は1年2年の流年の事象ではないのです。「今年はいい歳だからノーベル賞がもらえる」といったことは当然のようにないのです。
ただ、素晴らしい研究を成し遂げ、ノーベル賞の選考対象になるまで、数十年かかります。ですから、ノーベル賞授賞者に高齢者が多いことにもなるのです。iPS細胞で受賞した山中伸弥博士は異例です。
少なくとも言えるのは、優れた研究をした学者がノーベル賞を受賞するには、ある程度長生きする必要があることになります。これも必要条件でしかありませんが。
※上記の説明には、本書独自の蔵干の考え方と、格局に代わる」「旺の逆転」という視点が含まれています。詳しくは、基礎から最高峰を目指す『四柱推命の本』を参照してください。
2014・10・10
Since:1998-08-05 /// Last updated:2023-8-2
著作権法に基づき、本サイトの内容を、無断で引用、複製、翻訳、放送、出版、改変、等することを禁じます。
- 参考文献 |
- お問い合わせ
- | 管理人Profile
- |ツイート